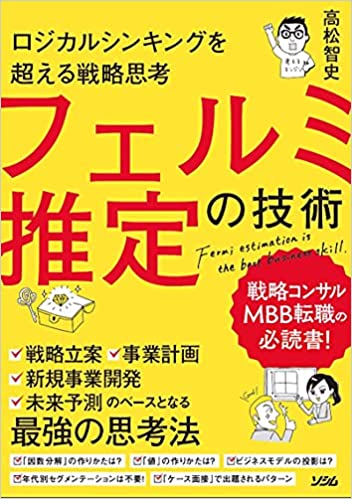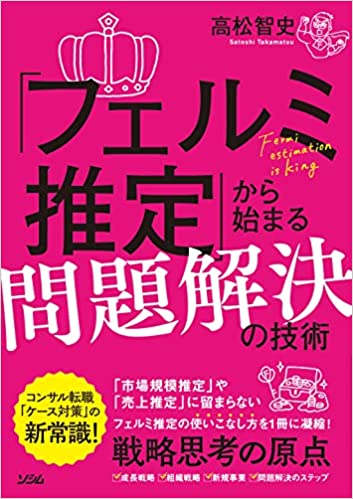【フェルミ推定の罠】市場規模算出に必要な頭の使い方を5つのステップで完全攻略

【フェルミ推定の罠】市場規模算出に必要な頭の使い方を5つのステップで完全攻略
フェルミ推定とは?
はじめに
フェルミ推定とは、実際に調査することが難しいような捉えどころのない量を、いくつかの手掛かりを元に論理的に推論し、短時間で概算することである。
ウィキペディアより
フェルミ推定とは、
日本のコインロッカーの市場規模はどのくらいか?
といったお題に対し、5~10分で “〇〇億円!” と数字を出す、典型的なコンサルケース面接の一つです。苦手だ!!という方、多いのではないでしょうか?
実は、少し前であれば、ケース面接で「新卒」にしか出なかったフェルミ推定ですが、嬉しいことに昔より “コンサルタント” という職業が市民権を得て、コンサルタントへの転職がメジャーになったことで、「箸にも棒にもかからん」という方も受けるようになりました。
その足切りも兼ねて、ケース面接の序盤にフェルミ推定の問題が出されることが多くなっています。
だから、、、フェルミ推定対策は必要。
そして、ケース面接のためだけでなく、実際にコンサルタントになってからも「フェルミ推定」に必要な頭の使い方は重要です。
実際にBCGで過ごした8年間でも、何度か、市場規模を推計してきました。だから、コンサルタントになってから活躍する上でも「正しく」理解しておいたほうがいいのです。
だし、フェルミ推定は「ロマン」なんです。
気持ちいいくらい、明確に回答できるもので、もう、スカッとします。
ここでは、年間500人以上にご受講いただいている「考えるエンジン講座」受講生が門を叩いたばかりの時に導き出した「おかしな回答」を例に挙げながら苦手だと感じている方が多い、フェルミ推定の解き方、また、ハマってしまいがちな罠について紹介していきたいと思います。
【5つのステップ】フェルミ推定攻略を完全攻略

5つのステップで進めていきますので、フェルミ推定を攻略したい気持ちがあるのであれば、前から順に、じっくり読み進めていってください。
5つのステップ
- まず、問題を解いてみる
- 様々な問題の回答例を見てみる
- フェルミ推定で陥りがちな「6つの罠」を知る
- フェルミ推定で陥りがちな「6つの罠」を知った上で、回答例への指摘をじっくり読む
- 回答例に自分で指摘をする
フェルミ推定完全攻略-ステップ1『まず、問題を解いてみる』
それでは、まず1問チャレンジしてください。 まじめに自分で解いてから、この先を読んだ方がより深く理解できます。 逆に言えば、やらずにこの先に進むと 「こんな罠、ハマらない」 と思ってしまい、ご愁傷様に。
だから、全力で解いてみましょう。
例題:フェルミ推定を用いて市場規模を算出してみる
日本のコインロッカーの市場規模はどのくらいか?(制限時間10分)
もう一度言います。まじめに自分で解いてから、この先を読んだ方がより深く理解できます。
10分考えきったら次に進んでください。
きっちり、10分間考えてみると、”10分て意外と長い!” と思った人、”答えまで出なかった!” という人、様々かと思います。
では「罠」について学んでいただくために、次にいくつかこの問題の回答例をご紹介していきます。
フェルミ推定完全攻略-ステップ2『様々な問題の回答例を見てみる』
さて、それでは、実際に「考えるエンジン講座」受講生に解いていただいた回答例を見ていきましょう。
これからご紹介する4つの回答例は、決して出来の悪い回答を集めたわけではありません。
みんな「“通常”こんなレベル」だと思ってご覧ください。
回答例①「日本に温泉旅館は何軒くらいありますか?」
日本にある温泉旅館はだいたい6000軒です。どうやって計算したかというと、1年間で何人の客が日本の温泉旅館を利用するか÷旅館1軒あたりの1年間で客が利用する人数です。
1年間で温泉旅館を利用する客は1億2000万人、1軒あたりの1年間で客が利用する人数は20000人です。
もう少し説明すると、議論となるのは、1軒あたりの1年間の客の利用人数で、もう一段回分解すると、温泉旅館の1軒あたりの部屋数×その部屋の収容人数×温泉旅館の稼働率、さらにいうと、1軒あたりの部屋数は、温泉旅館の階数×温泉旅館の1階あたりの部屋数、で算出します。
それぞれ説明すると、温泉旅館の階数はだいたい5階、温泉旅館の1階あたりの部屋数はだいたい10部屋、その部屋の収容人数は2人、温泉旅館の稼働率は6割(平日を5割、休日を9割とした平均)、1年間で温泉旅館を利用する客は1億2000万人(日本人一人が年間に必ず1回は温泉旅館に行く、とする)、なので、日本の温泉旅館はざっくりいうと、12000万人÷(5階×10部屋×2人×60%×1年)=約6000軒、となります。
回答例②「東京都内ではタクシーは何台あると考えられますか?」
東京都内にあるタクシーは約5万台あると考えられます。
どうやって計算したかというと、東京都内で夜間に駅で客待ちしているタクシーの台数×東京の駅の数×2(昼間と夜間で2交代制であると仮定)です。東京都内で夜間に駅で客待ちしているタクシーの台数は40台、東京の駅の数は600です。
もう少し説明すると、議論となるのは、東京都内で夜間に1駅あたりの客待ちしているタクシーの台数で、もう一段回分解すると、東京都内の駅の出口の数×東京都内の駅の出口に夜間客待ちしているタクシーの台数であり、さらにいうと、東京都内の駅の出口に夜間客待ちしているタクシーの台数は、12-1時の客待ちのタクシー台数+1-5時の客待ちのタクシー台数で算出します(始発から終電まで)。
時間帯によって台数が大きく異なるため場合分けしました。それぞれ説明すると、東京都内の駅の出口の数は2つ、1つの出口ごとに客待ちしているタクシーの台数は12-1時の客待ちのタクシー台数が10台、加えて1-5時の客待ちのタクシー台数10台=20台となります。よって、東京都内で夜間に1駅あたりの客待ちしているタクシーの台数は40台。
なので、東京都内にあるタクシーの台数はざっくりいうと、40×600駅(品川区の人口40万人あたり20駅あることから、人口2万人に一駅あると計算)×2=約5万台と考えられます。
回答例③「携帯電話保険事業の粗利率はいくらか?」
携帯電話の保険事業の粗利率は70%と想定します。
この事業は加入者からの支払い料金が売上、携帯破損時の新品提供・修理費用がコストで差分が粗利益という収益構造となっています。
考え方として、月額の売上2,000万円に対し、新品提供・修理費用等のコスト800万円がかかっており、粗利益1,200万円、粗利率60%と算出しました。
それぞれ説明すると、まず売上は、保険加入者を10,000人、月額の支払い料金を平均2,000円にて2,000万円と算出しました。
次にコストですが、まず交換対応は、1年に1回交換依頼があると仮定して10,000人×1/12=800回あるとします。1回あたり、新品提供は15,000円、修理は5,000円とします。修理で対応できる割合が50%とすると、コストは400回×15,000円+400回×5,000円=800万円と算出しました。
従って、粗利益は売上2,000万円-コスト800万円=1,200万円(60%)となります。
回答例④「携帯電話の事業の粗利率はいくらか?」
まずは事業の粗利率についてお答えします。粗利率は約8割と推定されます。
考え方としては、売上は保険料であり、対応するコストは修理に使用する部材と交換するときの端末原価ですが、保険料を支払っている加入者のうち、携帯を壊す人の割合と、その結果修理となる割合と交換となる割合を考慮してコストを算定しました。
具体的には、保険料の方は月額500円と仮定し、保険期間を2年とすると合計保険料は12,000円です。
一方で、加入者のうち機種変更前に携帯を壊す人の割合を5人に1人と仮定します。また、携帯を壊した加入者のうち、修理で済む人と全交換となる人の割合を半々とします。修理にかかるコストを5,000円、機種交換にかかるコストを20,000円と仮定すると、確率を考慮した想定コストは2,500円となります。
従い、粗利率は約8割となります。
実際に「考えるエンジン講座」受講生の“受講前”の回答を4つ紹介させて頂きました。みなさん、どこが、いけないのか?どんな罠にハマっているのか?お気づきになりましたか?
もし、「結構、これ、よくできてるんじゃない?」と思ってしまったアナタ。。。
では、次に具体的にフェルミ推定で陥りがちな“6つの罠”についてご紹介していきましょう。
フェルミ推定完全攻略-ステップ3『フェルミ推定で陥りがちな「6つの罠」を知る』
フェルミ推定の罠1=タイムアップ!答え、出ませんでした!
え?そんなことあるの?とお思いかもしれませんが、実際よくあること。
なにせ、フェルミ推定!は5~10分で答える必要がある上、緊張感も高いので、「因数分解していたら、時間が来てしまった」となってしまいがち。ですので、なにがなんでも、答えを出す!
答えを出す前に途中で終了してしまっては、まさに、罠1=タイムアップ!
とにかく何が何でも答えを出す!どんなにチープになっても、答えを出す!
これ、コンサルタントの基本です。
フェルミ推定の罠2=因数分解したぜ、どや!!!
① 因数分解したらいいんでしょ?
って、思っているヒト、本当に多い。罠にハマっております。
確かに、因数分解は必要ですが、「大の大人が!」とは言いませんが、コンサルを目指そう!っていう人だったら、因数分解なんて、だいたい同じになると思いませんか? でしょ。思うよね。
なのに 因数分解したぜ、どや!!! と、どや顔されても困るわけです。なにせ、みんな、ほとんど同じように分解するんだから。
じゃ、どうすればいいか?紹介していきます。
② じゃ、どうすればいい?
複数の因数分解、だいたい2つくらい案を考えて、そのうち、先を見越して、選択する。
例えば、温泉旅館でいえば、
A:温泉にいくのべ回数 ÷ 1つの温泉旅館の年間キャパシティ
B:温泉街の数 × 1つの温泉街にある温泉旅館の数
一見、Aの方がいいと考えがちですが、「温泉にいくのべ回数」っていうのが本当にやっかいで、結局、「自分は年2回行くので、2回と置きました」的、主観的になってしまう。
ので、この場合はBのほうがいい。
もう少し説明すれば、相手に温泉旅館数の算出方法を説明したときに、どちらが「ピンと来てくれるか?」が大事。だから、Bのほうがピンとくるし、数字も置きやすい。
しかし、大切なのはあくまで「2つ以上、因数分解を考えて、どっちがいいかな?」と考えること。それこそが、「頭を使う」ってことになる。作業ではなくね。そこは、お間違えなく。決して、論点を間違えない。
「いかに、正しい数字を出すか?」ではなく「いかに、ピンとくる数字を出すか?」なのです。
フェルミ推定の罠3=因数分解バカっ
① 因数分解を “こまかく” したら、いいんでしょ?
これも多い。因数分解の価値は「細かさ」=どんだけ、因数に分解されているか?と思っているひとが、まぁ、多い。これは間違い。
さらに、問題なのが、因数分解しまくっている部分で誰もが因数分解を「しやすい」ところばかりをやる。その中でも一番多いのは、日本の人口=1億2千万人から始まって、年代に分けて、男女に分けてと、あたかも、それを時間をかけまくり、すごいでしょ!的な感じ。

さぶい。さぶいよ。そんなの誰でもできるから!
大事なのは「どのように因数分解をするか?」 そこに「頭の使い方」が表れるわけです。 議論になる=クライアント(=ケース面接でいう“面接官”)が 「この数字、どうやって出すんだろうな?難しいな・・」 ってところを分解すべき。
では具体的に「どのように因数分解をするか?」を説明していきます。
② どのように因数分解をするか? (1)
例えば、回答例①「日本に温泉旅館は何軒くらいありますか?」でいえば「温泉旅館を利用する客」を分解しなければなりません。
もちろん、「旅館1軒あたりの1年間で客が利用する人数(⇒これより、旅館のキャパシティにしたいけど)」のほうが簡単だし、ピンとくる。 だからこそ、相手にとっても知りたい=議論になる「温泉旅館を利用する客」を頑張って分解してほしいということ。
なので、先ほど紹介した下記の回答が、いかに残念か?がわかるはずです。
回答例①「日本に温泉旅館は何軒くらいありますか?」【再掲】
日本にある温泉旅館はだいたい6000軒です。どうやって計算したかというと、1年間で何人の客が日本の温泉旅館を利用するか÷旅館1軒あたりの1年間で客が利用する人数です。
1年間で温泉旅館を利用する客は1億2000万人、1軒あたりの1年間で客が利用する人数は20000人です。
もう少し説明すると、議論となるのは、1軒あたりの1年間の客の利用人数で、もう一段回分解すると、温泉旅館の1軒あたりの部屋数×その部屋の収容人数×温泉旅館の稼働率、さらにいうと、1軒あたりの部屋数は、温泉旅館の階数×温泉旅館の1階あたりの部屋数、で算出します。
それぞれ説明すると、温泉旅館の階数はだいたい5階、温泉旅館の1階あたりの部屋数はだいたい10部屋、その部屋の収容人数は2人、温泉旅館の稼働率は6割(平日を5割、休日を9割とした平均)、1年間で温泉旅館を利用する客は1億2000万人(日本人一人が年間に必ず1回は温泉旅館に行く、とする)、なので、日本の温泉旅館はざっくりいうと、12000万人÷(5階×10部屋×2人×60%×1年)=約6000軒、となります。
② どのように因数分解をするか? (2)
次に、回答例③「携帯電話保険事業の粗利率はいくらか?」でいえば因数分解すべきは「加入者からの支払い料金」や「修理費用」ではなく、「修理頻度」です。
なので、先ほど紹介した下記の回答が、いかに残念か?がわかるはずです。
回答例③「携帯電話保険事業の粗利率はいくらか?」【再掲】
携帯電話の保険事業の粗利率は70%と想定します。
この事業は加入者からの支払い料金が売上、携帯破損時の新品提供・修理費用がコストで差分が粗利益という収益構造となっています。
考え方として、月額の売上2,000万円に対し、新品提供・修理費用等のコスト800万円がかかっており、粗利益1,200万円、粗利率60%と算出しました。
それぞれ説明すると、まず売上は、保険加入者を10,000人、月額の支払い料金を平均2,000円にて2,000万円と算出しました。
次にコストですが、まず交換対応は、1年に1回交換依頼があると仮定して10,000人×1/12=800回あるとします。1回あたり、新品提供は15,000円、修理は5,000円とします。修理で対応できる割合が50%とすると、コストは400回×15,000円+400回×5,000円=800万円と算出しました。
従って、粗利益は売上2,000万円-コスト800万円=1,200万円(60%)となります。
フェルミ推定の罠4=勘、かよっ
① 分解したら、あとは「勘」で数字を置く
実に、これまたハマっている人が多い。
なぜかというと、罠1、罠2にハマって、エネルギーを「因数分解」に取られ、「どんな数字を置けばいいか?」まで、意識も時間も使えてないから。 だから、肝心のところを「勘」でおく。
1年間で温泉旅館を利用する客は1億2000万人。日本人一人が年間に必ず1回は温泉旅館に行く、とする。
ちょいまてぃ!
となるのだ。
そこ、そこを考えろ!って言っているのに、そこを「~とする」ではない。ここが「腕の見せ所」。
罠4にはまらないために、一つ、フェルミ推定!の定義に原点回帰してみましょう。
② フェルミ推定!の定義に原点回帰
フェルミ推定!とは、 未知の数字を論理と常識をよりどころに、 推定する問題である
「外資系コンサルの面接試験問題過去問で鍛える地頭力」(東洋経済新報社)
つまり、「常識をよりどころに」するしかないのです。
だから、勘ではなく、無理やりでもいいから、知っていることを根拠に置くことが大事。
その数字が当たっている?当たっていない?は二の次で、自分の常識・知識をベースに思考を回すことができれば、それでいいのです。
フェルミ推定の罠5=コトバ、乱れすぎっ
① 「話し方」が疎か。
ほんとに、「話し方」を疎かにしていませんか?
特に、書籍で学んでいると、「解くこと」にフォーカスしすぎて、「話し方」疎かになってしまいます。
ここで、いい言葉をお教えいたします。
コトバが整えば、シコウが整う。
シコウが整えば、コウドウが整う。
コウドウが整えば、ジンセイが整う。
まさに、 コトバが整えば、シコウが整う。
ですので、フェルミ推定!は特に、 「どのように解くか?」以前に、「どのように説明するか?」で、シコウの整い具合が解るのです。だから、よくあるのが、 因数分解に意識がいって、何言っているか、分からない人。
ご愁傷様!チーンとなってしまいます。
コトバを整える、これ、コンサル転職の第一歩。
では、どう答えるのが、セクシーなのか?の一例をご紹介していきます。
② どう答えるのが、セクシーなのか?(例:銭湯の市場規模)
市場規模は400億円です。
どうやって計算したか?というと、 銭湯の数 × 1つの銭湯の一年間の売上高 で出します。
それぞれの数字は、 4000個 × 1000万円 となり、単純計算で400億円です。
特に論点になるのが、銭湯の数なので、さらに分解すると、 銭湯の数は、 駅の数 × 1つの駅にある銭湯の数 で出せます。
駅の数が4000個、1つの駅には1つ銭湯があるとし、4000個となります。
「式を示すこと」→「それぞれの数字を示す」ことで、相手の頭に入りやすいのです。話し方は本当に大切。

「考えるエンジン講座」でも、徹底的にコトバを整える。
それは、ケース面接においても、コンサルタントとして活躍する上でも、大事なことです。
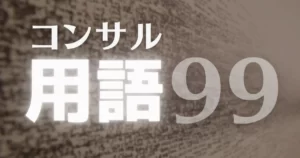
フェルミ推定の罠6=フェルミボンっ
「フェルミ推定!本」 is キング
世に溢れるフェルミ推定本はよくできている。なにせ、本として出版するわけだから、 間違ってはいけない。本当に「正しい」答えを載せないとだめだ。 だから、フェルミ推定本は、役に立たないのだ。
え?どういうこと?
解答を読んでいるとよく思うのだが、「答えを知っているひと」が作った解答だな~と。 グーグル先生に聞いて、答えを知った上で、因数分解も、数字の置き方も「やっている感」が感じられる。
それではだめなのだ。
フェルミ推定とはあくまで「この世に答えがない」「答えなんて、分からない」ときに “それっぽい”数字をたたき出す頭の使い方なんだから、それだと、勉強にならない。
なので、こんな思いから、フェルミ推定の本を出版してしまいました。これだけ言ったんだから、もちろん、みなさんに満足してもらえる本にしましたよ。
『ロジカルシンキングを超える戦略思考 「フェルミ推定の技術」』
先の見えない世の中において、“積み上げる”ロジカルシンキングよりもパワフルであり、“もれなくだぶりなく”なMECEよりも、答えの無いゲームに強い思考法。それが、フェルミ推定です。
ロジカルシンキングの次は “フェルミ推定” の時代です。
コンサル転職でのケース面接に必須のフェルミ推定ですが、ビジネスパーソンにこそ絶対に必要な、ビジネススキル。本書から最強の戦略思考を手に入れてください。様々な視点から導き出した「フェルミ推定の技術」を詰め込んでいます。
高松 智史 (著)
出版社 : ソシム
発売日 : 2021/8/18
単行本 : 324ページ
『「フェルミ推定」から始まる問題解決の技術』
「フェルミ推定」は、市場規模推定や売上推定を算出する為だけの思考法じゃありません。成長戦略、新規事業などに幅広く応用できる、いわば戦略思考の原点とも言えます。そして、その考え方を丸っと凝縮して一冊にまとめたのが本書です。
今までの「ロジカルシンキング」や「問題解決」書とは全く違う、プラクティカルでわかりやすい、新しい問題解決本がここに誕生しました。
高松節が炸裂しまくりの、最高に読みやすくセクシーなビジネス書。ビジネススキルの新境地としてのフェルミ推定を、ぜひ堪能してください!
高松 智史 (著)
出版社 : ソシム
発売日 : 2022/2/26
単行本 : 320ページ
フェルミ推定6つの罠 まとめ
ここまでを振り返ると
罠1=タイムアップっ
罠2=因数分解どやっ
罠3=因数分解バカっ
罠4=勘、かよっ
罠5=コトバ、乱れすぎっ
罠6=フェルミボンっ
うん。皆さんも、きっとハマってることだろう。

あともう一つ、最後にフェルミ推定に限った話ではないですが、大きな罠をご紹介します。
フェルミ推定 もう1つの罠
フェルミ推定!ごときができないがゆえに、一生に一度しかチャンスのない「コンサル転職」を棒に振るわけにはいきませんよね。あんまり知られてないのかもですがコンサル転職は “一生に一度しか” チャンスがありません。
“公式発表” では、1年経てば、同じコンサルティングファームでも受けることができる。しかしながら、そうは問屋が卸さない。
コンサルティングファームの採用面接にはものすごく手間(≒お金)がかかります。くっそ忙しいマネージャー以上が時間を取らねばならない。そもそも、年間に面接できる人に限りがある。かつ、毎年、ものすごい数の応募がある。だから、 一度見た人は、そうそう見ない!コンサルティングファーム側に立てば、合理的で納得です。

一生に一度のチャンスを逃さないよう、ちゃんと「考える力」を鍛えてから望みましょう。
フェルミ推定完全攻略-ステップ4『フェルミ推定の罠を知った上で、回答例への指摘をじっくり読む』
一般的に合っていると思われているフェルミ推定の回答例をイチイチツッコんでみました。まずはあなたが解いてみてください。
6つの罠を学んだところで、もう一度、解いてみましょう。
自分の成長を感じられたら、それは素敵なこと。
フェルミ推定例題:マッサージチェアの市場規模は?(制限時間20分)
成長するために、必ず20分考えきってください。
お疲れ様でした。それでは、今度は、別の方たちの7つの回答をじっくりみてみましょう。
フェルミ推定回答例①~⑦にツッコんでみました
フェルミ推定完全攻略-ステップ5『回答例に自分で指摘をする』
フェルミ推定例題:マッサージチェアの市場規模は?回答例にツッコむ

では、今度は皆さんが、次にご紹介する回答例8~15までにツッコミをいれてみてください。
ここで、6つの罠を改めて確認してみましょう。
罠1=タイムアップっ
罠2=因数分解どやっ
罠3=因数分解バカっ
罠4=勘、かよっ
罠5=コトバ、乱れすぎっ
罠6=フェルミボンっ
6つをアタマに叩き込めましたか??
ではでは、、、少し “嫌なやつ” になりきって、指摘してみましょう。
フェルミ推定回答例 ⑧=マッサージチェアの市場規模は336億円
マッサージチェアの市場規模は、336億円であると考えます。
市場規模を考えるにあたり、大きく個人消費と法人消費に分けて検討していきたいと考えます。
個人の場合
個人の場合、 世帯数×シェア率×単価×買い替え率で市場規模が算出できます。
個人でマッサージチェアを購入するのは、40歳以上のファミリー層でしょう。
例えば、45歳がお父さんの家庭を考えてみますと、子供も中高校生となり、仕事で事務作業が増え、慢性的な肩こりに悩まされるときだと思います。また、お母さんも肩こりに悩まされる年頃であると思 います。1家に1台あればいい方でしょうか。平均価格は20万円。
シェア率を考えますと、40歳ファミリーのうち、どれくらいが持っているのでしょうか。
マッサージチェア本体を考えてみますと、かなり場所をとるものであることが分かります。かつ廃棄も面倒なので、一度買ってしまえば、あまり買い替えることはないでしょう。また、20万円もする高価なものなので、比較的裕福な家庭となります。 そうすると、都心で狭い家に住んでいるファミリー層では、マッサージチェアは購入しないであろうと推察されます。つまり、郊外で持ち家の広い家に住んでいるファミリー層かつ、世帯年収が500万円以上の家庭にて、マッサージチェアを購入していると考えられます。 具体的に、計算していきます。
- 40歳以上ファミリー世帯数: 120,000,000(日本人口) × 4/8(人口を80代までとし、40代以上の割合) × 1/2 (2以上の世帯) = 3000万世帯
- 持ち家に住んでいる= 60%
- 郊外に住んでいる= 80%
- 年収500万円= 9%
- 単価: 20万円 買い替え率= 10年
計260億円 が個人消費におけるマッサージチェアの市場規模と考えます。
法人の場合
法人の場合、施設数 × シェア率 × 単価 × 買い替え率で市場規模が算出できます。法人でマッサージチェアを購入するのは、スパや温泉旅館の温泉施設に設置していると考えます。
施設ですが、日本人口に対して、温泉に行く需要を満たすことが施設数を考えます。
温泉に行く人口を1億人とします。温泉施設の規模ですが、大体1旅館15部屋ほど存在していると考えますと、一日当たり30人の宿泊が可能です。さらに、稼働率を60パーセントとします。1億人/泊 ÷ (30人×365) ÷ 0.6= 15,221件の施設が全国に存在しております。
一件当たり、20万円のマッサージチェアを5台保持しているとして、買い替え率を5年としますと、76億円が法人におけるマッサージチェアの市場規模となります。
結果、260億円+76億円= 336億円 がマッサージチェアの市場規模と考えます。
フェルミ推定回答例 ⑨=マッサージチェアの市場規模は281億円
マッサージチェアの市場規模は281億円と想定されます。
まずは、考え方を説明させてください。
マッサージチェアの購入主体は大きく二つあります。一つは各世帯であり、もう一つは銭湯やゴルフ場といった共用施設です。それぞれが日本にどのくらいの数があるかを最初に考え、世帯数と施設数に単位あたりのマッサージチェア保有数を掛けて、全体のマッサージチェア数を算出します。
平均マッサージチェア数に単価を掛けて、最後にマッサージチェアの平均使用年数で割ることで1年あたりの市場規模が算出されます。
次に、具体的な計算過程を説明させてください。世帯数は日本の人口1億2千万人を前提とし世帯あたりの平均人数を3人として、4,000万世帯とします。マッサージチェアがある共用施設の数ですが、各都道府県あたり100施設として、4,800施設とします。
マッサージチェアを保有している世帯は10世帯に1世帯とし、各共用施設には施設あたり平均3台のマッサージチェアがあるとします。
そうすると、世帯と共用施設のマッサージチェア台数合計は4,014,400台となります。
次に、マッサージチェアの平均単価を7万円とし、平均使用年数を10年とすると、市場規模は281億円と算定されます。
フェルミ推定回答例 ⑩=マッサージチェアの市場規模は600億円
日本におけるマッサージチェア市場規模は600億円と推測します。
まず市場規模は、マッサージチェア1台の平均単価×年間購入台数で算出できますので、それぞれの数値の算出の仕方について説明していきます。
最初に、マッサージチェア1台の平均単価ですが、ヨドバシカメラなどの販売ルームに行くと、最近は全て電動式しか置いておらず、椅子でマッサージするものから、フラットになって指圧・もみほぐし・たたきなど様々なパターンを選べるものもあり価格10万円台から高いのは50万円まであります。ここでは平均単価30万と設定します。
次に、年間の購入台数ですが、マッサージチェアは空港やスポーツジムなどにも置いてありますが、法人向けはマッサージチェア市場全体の一部かと思いますので、ここでは家庭向けマッサージチェアの個人消費に絞って考えます。
まず、購入台数を構造化すると、日本の世帯数×購入比率×購入数/世帯×購入頻度(交換)で表せます。日本の世帯数は4000万世帯、1世帯の購入数は1台とします。2台購入はきわめて稀ですので。
次に実際に購入する比率ですが、購入メイン世帯はある一定以上の富裕層と考えます。
大凡1メートル×1メートルのマッサージチェアを家に置くスペースが必要な事を考えれば、2LDK以上の広さに住む世帯が対象で、仮に世代と収入が一定の比例関係にあるとすれば、若手の1人暮らしやカップルは対象とならず、恐らく生活に余裕ある40代以上の世帯でしょう。40代以下の世帯数と40代以上の世帯数が同じと仮定すると、マッサージチェアを購入可能な割合は4000万世帯×50%=2000万世帯と絞り込まれます。
この内、実際に購入する割合はどのくらいか、を考えます。恐らく実際に購入する人は「どうしても買いたい」という強い意志がある人でないかと考えます。マッサージチェアを購入する代わりに自分でマッサージしたり、整骨院に行くなどできますし、スペースや金額を考えると家族の説得が必要です。これら、代替えや制約条件を考えても、尚、購入する割合はかなり限られてくるでしょう。従ってここでは対象顧客の5%が実際に購入すると推測します。
最後に購入の頻度ですが、マッサージチェアが何度も交換するものではないので、5年に1回の頻度で購入・交換するとします。 以上の条件を合わせると、マッサージチェアの年間購入台数は、4000万世帯×50%(購入対象比率)×5%(実購入比率)×1台/世帯×0.2(5年に1回購入)=20万台と推定できます。
マッサージチェア1台30万円ですので、市場規模は30万円×20万台=600億円となります。
フェルミ推定回答例 ⑪=マッサージチェアの市場規模は938億円
- 日本の国内市場に絞って考え、その市場規模は、938億です。
- 65歳以上のシニア人口と20~65歳未満の一般人口から市場を割り出すことで市場規模を予測しました。(シニアがコアターゲット、一般がサブターゲットと考えたため)
下記が、それらの仮定です。
- 日本の人口を1.2億人
- 30%が65歳以上:3,600万人⇒約3%が購入する⇒約110万人(メインターゲット)
- 40%が20歳~65歳未満:4,800万人⇒0.5%が購入する⇒24万人(サブターゲット)
また、マッサージチェアの価格は、ローモデルからハイエンドまであるが、平均70,000円と仮定しました。
よって、市場規模は、 134万人×70,000=938億 中古市場は、ローエンドなモデルと同じくらいの価格で販売されていると考えることで、新品市場に包含されると考えております。
フェルミ推定回答例 ⑫=マッサージチェアの市場規模は1500億円
マッサージチェアの市場規模は1500億円です。
この市場規模を算出した計算式は「一般家庭のマッサージチェアの総保有台数×単価×買替の頻度」です。
それぞれの因数についてご説明します。
「一般家庭における総保有台数」は「日本の世帯数×マッサージチェアの保有割合」で求めました。
日本の世帯数は約5,000万世帯と仮定しました。
保有割合はマッサージチェアが嗜好品かつ高価格であることを考慮し、10世帯に1世帯が保有していることとし1/10と仮定しました。
以上より、「一般家庭における総保有台数」は50,000,000÷10=5,000,000です。
次の因数である「単価」については高価格帯の価格を50万円、低価格帯の価格を10万円と仮定し、平均を取って、30万円と考えました。 最後因数である「買替の頻度」について、ご説明します。
「買替の頻度」はマッサージチェアが大型の電化製品であることから10年に1度程度買い替えるものと仮定しました。
以上より、「マッサージチェアの総保有台数×単価×買替の頻度」は5,000,000台×300,000円÷10となり、1500億円です
フェルミ推定回答例 ⑬=マッサージチェアの市場規模は460億円
マッサージチェアの市場規模を求めるにあたり、マッサージチェアには家庭用(世帯所有)と業務用(法人所有)がありますが、今回は世帯で所有しているマッサージチェアに限定して考えたいと思います。また、市場規模とは、日本での1年間の売上規模のことであるとします。
マッサージチェアの市場規模 = マッサージチェアの平均価格 × 1年間で購入された台数 で求めることができますが、1年間で購入された台数を更に分解すると、
1年間で購入された台数= ①新規購入台数 + ②買い替え台数
<①新規購入台数>
① 新規購入台数 = 世帯数 × 新規購入率 × 平均購入台数
で求められます。ここで、世帯数は日本の人口が1.2億人で平均世帯人数を3人と仮定すると4,000万世帯となります。マッサージチェアは比較的高価な商品ですから、新規購入率は1%、平均購入台数は1台と仮定すると、
① 新規購入台数 = 4,000万世帯×1%×1台 = 40万台
<②買い替え台数>
①買い替え台数 = (ストック/耐用年数)× 買い替え率 × 平均購入台数
で求められます。ここで、現在、マッサージチェアを所有しているのは全世帯(4000万世帯)の3%と仮定すると、ストックは120万台。耐用年数は10年と仮定し、マッサージチェアは比較的高価な商品ですから、買い替え率は半数の50%、平均購入台数は1台と仮定すると、
②買い替え台数 = 120万台/10年 × 50% × 1台 = 6万台
以上から、1年間で購入された台数は40万台+6万台で46万台。
マッサージチェアの平均価格を10万円とすると、マッサージチェアの市場規模は、
マッサージチェアの市場規模 = 10万円×46万台=460億円
フェルミ推定回答例 ⑭=マッサージチェアの市場規模は73億円
マッサージチェアの市場規模はいくらか、ですが、年間約73億円と試算しました。
計算の方法は、年間の販売台数xマッサージチェアの平均単価です。
特に年間の販売台数についてご説明すると、年間の販売台数については、需要全体を償却年数で割ったものとして想定しました。
ではマッサージチェアの需要全体がどの程度かですが、需要は大きく個人と法人に分けることができます。
まず個人については、私の周囲の友人の世代ではマッサージチェアを持っている家庭はほとんどなく、またそれなりに世帯年収の高いと思われる私の友人の親の家庭でもほとんどなく、働き世代だとするとかなり世帯年収の高い少なくとも1500万円以上の世帯か、一定の資産を有する高齢者世帯、こちらも元々は年間1500万円以上程度の収入があり、それなりの資産のある高齢者世帯が主な需要者だと考えられます。
それぞれがどの程度の需要を持つかについてですが、日本の世帯数が4000万世帯だとすると、その5%程度が年収1500万円以上に当たると仮定します。そのうちの10%の世帯がマッサージチェアを購入すると仮定して、個人の需要は4000万x5%x10%=20万台です。
次に法人についてですが、およそマッサージチェアを使用する法人としてあげられるのは、温泉旅館、銭湯、老人ホームだと思います。それ以外もありえますが、無視できる量ではないでしょうか。
ではそれぞれがどの程度の需要があるかですが、平均して47都道府県にそれぞれどの程度あるかについて、温泉旅館を100か所、銭湯を250か所、老人ホームを500か所と仮定し、それぞれ平均して5個、2個、5個のマッサージチェアを有していると仮定すると、(100×5+250×2+500×5)x47=3500×47=16.5万台と成ります。
両方の需要を足し合わせると36.5万台となり、これを償却年数を仮に5年として5で割り、7.3万台、平均単価を10万円と仮定すると73億円となります。
フェルミ推定回答例 ⑮=マッサージチェアの市場規模は2.4億円
マッサージチェアの市場規模は、というと2.4億円/年です。
どう考えたか、というと市場規模を3つのサブ論点に分けました。
一つ目は平均利用単価は?、二つ目は平均利用時間/人は?、 三つ目はのべ利用者数は?です。
一つ目の平均利用単価は100円/10分が多く、10分/円としました。
次に、平均利用時間は利用者数の平均時間なので最低でも10分であり、5人に1人が20分と置き平均12分としました。
3点目は、国内旅行者数を2億人、利用率を1%と置きました。
市場規模
=(平均利用単価) x (平均利用時間/人) x (のべ利用者数)
=(10円/分)x(12分/人) x (国内旅行者数/年x利用率)
=(10円/分)x(12分/人) x (2億人x1%) =2.4億円/年

いかがでしょうか?指摘できましたか?皆さんも、こうなっているということです。ので、罠にハマらないように、正しくトレーニングしましょう。
フェルミ推定回答例集—無料ダウンロード
こちらでご紹介した15個の回答例をPDFでご用意しました。回答例8-15はご自身でツッコミを入れられるよう、回答欄を設けてあります。フェルミ推定のトレーニングにご活用ください。
「フェルミ推定の罠」解説動画

「フェルミ推定の罠」を動画でも解説しました。
僕が書いた「フェルミ推定の罠」を、考えるエンジンちゃんねるで動画で補足解説しました!
ここまで読んで、回答例でトレーニングした後に、動画を見ると、より、理解できます!
あわせて読みたい
2022年の慶応大学(環境情報)の入試にフェルミ推定が出題されたということで、「フェルミ推定」の著書2冊を出版しているボクとしては、解説せずにいられない!ということで、本気で解いてみました。
入試で出題されたフェルミ推定を解説-300x169.webp)